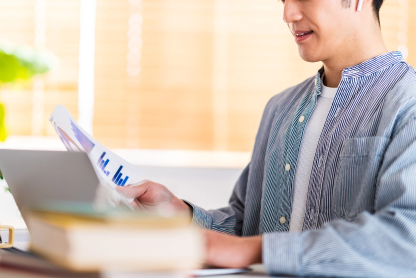エントリー
簡単なフォームから無料で登録できます。

ご登録面談
カウンセラーによる面談で、 ご経験やご希望をお伺いします。

案件をご紹介
ご経験、ご希望に沿った案件を、データ解析からマッチング。
経験豊富なカウンセラーの知見も踏まえ、随時、案件をご紹介します。

クライアントインタビュー
案件の詳細情報をヒアリング。不明点などの解消も行います。
日程調整や会議セットなどはBTCエージェントが行います。

契約締結
条件調整完了後、契約締結を行い、案件参画が確定します。
クライアントとの細かい条件調整はBTCエージェントが行います。

定期フォロー
評価フィードバックや契約内容に逸脱がないか等、定期的なMTGを実施することで、フリーランスとしての権利を守りつつ、スキル、キャリアアップをフォロー致します。